今回紹介するのは、金型メーカー「ミヨシ」。
一見どこにでもある町工場ですが、実は“下請け一辺倒からの脱却”と“挑戦する経営”という点で、非常に学びの多い企業です。
1.下請け依存の限界に直面
ミヨシは長年、下請け主体のビジネスモデルでした。
しかし、取引先の海外シフトやリーマンショックで売上が3分の1にまで激減。
社長が営業に行っても、「あなたに何ができるの?」と言われてしまう始末。
その原因は明確でした。
- 自社で発信できる商品や技術がない
- すべてが「言われたことを作るだけ」
- つまり、主体性のない“ただの作業工場”だった
社長はここで気づきます。
「自分たちで価値を生み出す力を持たなければ、生き残れない」と。
2.変革への挑戦と、従業員の大反発
そこで社長は、新たな事業に挑戦します。
しかしそれは利益度外視の取り組みであり、当然ながら従業員の残業負担が増加。
「なぜこんな儲からないことをやるんですか?」
「また社長が勝手に始めた」
と、大きな反発が起きます。
それでも社長は止まりませんでした。
- 新しいことには痛みが伴う
- しかし、スキルと知見こそが将来の武器になる
この“学びを重視する姿勢”こそ、ミヨシの大きな分岐点でした。
3.ミヨシの強みが花開く
もともとミヨシは「金型だけでなく成形までできる一貫体制」を持っていました。
さらに「特殊な形状を短納期・少量生産」で作れる技術力もあった。
この強みを活かし、試作品開発に軸足を移します。
- 医師の足腰の負担を軽減する器具
- ヨーグルトを残さずすくえるスプーン
- ベンチャーと共同開発した“カスタマイズできるロボット”
このロボットがSNSでバズり、認知度が一気に向上。
「下請けの町工場」から「アイデアを形にする開発工場」へと進化しました。
4.従業員の意識も変化
自社商品を生み出す中で、社員のモチベーションが大きく変わります。
- 「言われたものを作る」から
- 「自分たちのアイデアが形になる」へ
さらに、他の町工場と連携してものづくり体験イベントを開催。
自社の技術をSNSで積極的に発信。
“発信する側”に変わったことで、働く誇りも高まっていったのです。
5.診断士としての視点(私の提案)
ミヨシは大きなポテンシャルを持っています。
そこをさらに伸ばすには、以下のような方向性が有効です。
● IT化・データ活用
- 下請け事業と自社事業の売上・利益構造を「見える化」
- AIによる試作品シミュレーションでスピードと精度を向上
- 形状が似た試作品を標準金型化し、コストダウン
● ナレッジの共有
- 新技術やノウハウを社内でデータベース化
- 教育や共同開発のベースに活用
● 広げる(新市場展開)
- 医療・介護向けサポート器具
- DIYツール
- 精密パーツや福祉用品
● 川下へ踏み込む(直販・プラットフォーム化)
- 試作品依頼の「マッチングプラットフォーム」を自社で運営し、対応できない案件は他の町工場と連携し、ハブ企業になる
● コラボを仕掛ける
- デザイナー、エンジニア、設計者、メーカーなどとチームを組み、商品開発
- クリエイティブ人材を社外から招く(人材不足をカバー)
● 伝える力をさらに強化
- SNSで技術力を発信するだけでなく、
- リード獲得
- ファン育成
- 共同開発希望者の募集
- 採用ブランディング
- ここまで視野に入れた発信戦略を組む
● 組織力の強化
- 営業体制を整備し、「待つ会社」から「提案する会社」へ
- 自主事業と下請け事業を両立できる仕組み作り
6.まとめ:ミヨシが教えてくれること
- 下請け依存は安定ではなく「リスク」
- 自ら価値を生み出せる会社だけが選ばれる
- 新しい挑戦は反発を生むが、社員の誇りも同時に生む
- 強みを活かし、発信し、巻き込めば、大きな変化が起きる
そして何より、
「できることから始める」ではなく「やるべきことから始める」
この勇気こそが、経営を前に進める最大の力だと感じます。
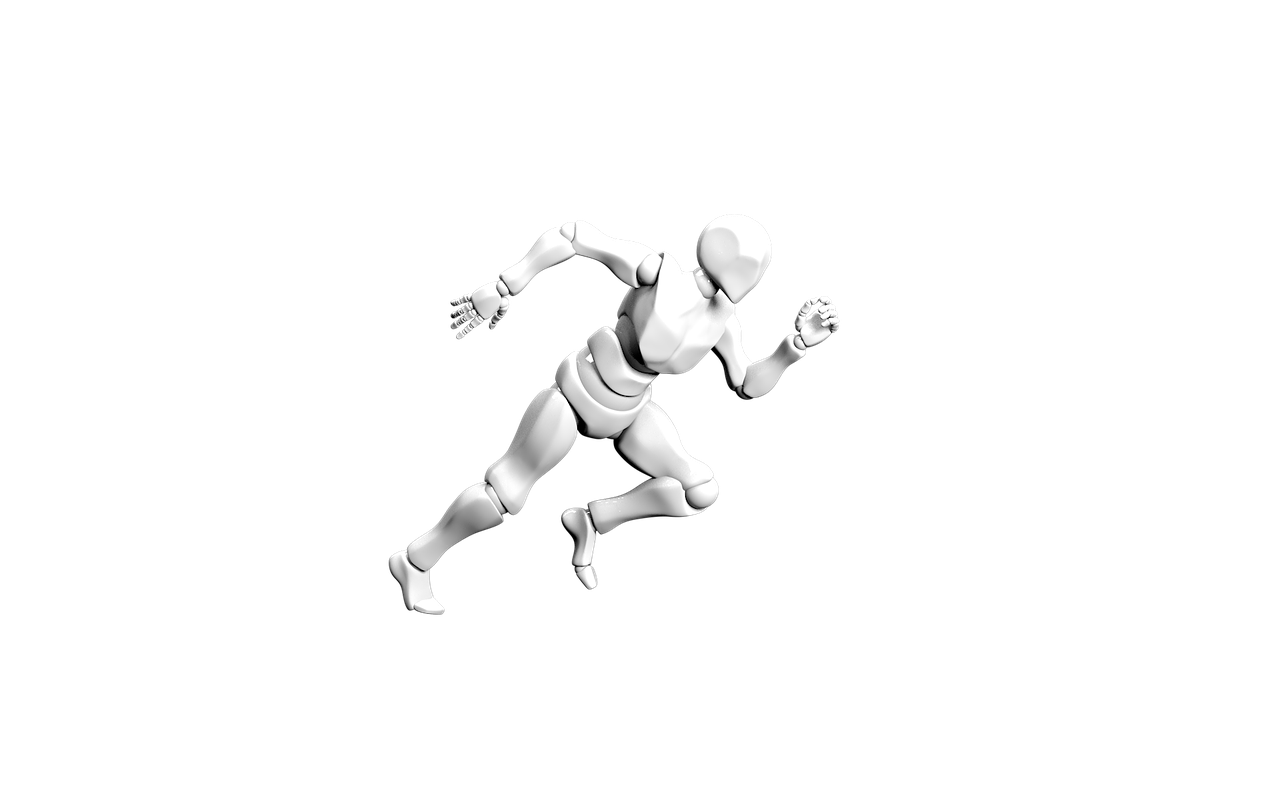


コメント