「大手メーカーの商品は置かない」「安売りはしない」「おいしいものしか売らない」
普通のスーパーマーケットとは真逆の戦い方で成功しているのが、群馬県の「まるおか」です。
最初は「そんなやり方で本当に大丈夫なの?」と思いましたが、実際は全国からファンが訪れるほどの人気スーパーに成長しています。
今回は、その裏側にある経営者の覚悟、強み、組織づくり、そして中小企業が学べるポイントを深掘りします。
経営者の決意:安さではなく「おいしさ」を軸にする
まるおかの転機は、「自分たちは生産者とお客様をつなぐ存在であるべきだ」と社長が気づいたことから始まります。
- 大手メーカーの商品を置かない
- 「おいしさ」だけで仕入れ判断
- 生産者の言い値で買い取る(値下げ交渉しない)
- 折込チラシによる安売りもしない
この方針に対し、多くの社員が反発し、退職者も続出しました。しかし社長はブレずに理念を貫きます。
「食は命。だから、おいしいものだけを届ける」
この強烈な信念こそが、まるおかの出発点です。
強み:圧倒的な「目利き力」と「おいしさの伝え方」
まるおかの最大の武器は、社長やバイヤーの“味覚”です。実際に自分たちで食べて、「本当においしい」と思ったものだけを仕入れます。
さらに、おいしさの伝え方にも工夫があります。
- POPはバイヤーの手作り
- 生産者の想いを載せる
- おいしい食べ方を提案
ただ商品を並べるだけでなく、「おいしさの背景」まで伝えるからこそ、価格が高くても売れるのです。
逆転の発想:「高く買って、高く売る」
普通のスーパーは「安く仕入れて、安く売る」が基本です。しかし、まるおかは真逆。
- 生産者の希望価格で買う
- その代わり、最高品質の商品を提供してもらう
- お客様には“価値あるもの”として正当な価格で販売する
このモデルにより、
生産者がやる気になる → 品質が上がる → お客様が感動する → リピートする → さらに良い商品が集まる
という「良い循環」を生み出しています。
組織づくり:理念を“毎日”伝える社長
このようなビジネスモデルを運営するためには、社員の理解と共感が欠かせません。
まるおかでは、社長が毎朝の朝礼で自らの思いを語り続けます。
「私たちは、おいしいものを作りたい生産者と、おいしいものを食べたいお客様をつなぐ存在です」
POPも外注ではなく、バイヤー自身が作ります。自分の言葉で商品を語るからこそ、説得力が生まれます。
理念はポスターではなく、「毎日の言葉」と「行動」で浸透するという好例です。
中小企業診断士としてのコメント
まるおかは「価値で勝つ」典型的な成功例です。ここから学べるポイントを診断士目線で整理します。
1. 強みを“価値”に変えている
「おいしさ」という感覚的な要素を、仕入れ基準・伝え方・商品構成に落とし込み、ビジネスモデルとして成立させています。
2. 組織文化を理念で統一
トップが理念を語り続けることで、社員も「なぜこの仕事をするのか」を理解しています。理念と行動が一致すると、現場は強くなります。
3. 逆張り戦略を“やりきる”覚悟
「安売りしない」「値引きしない」は簡単ではありません。退職者が出ても理念を貫いたことで、本当に価値を信じる人材が残りました。
4. まだまだ伸びしろがある
今後、さらに成長するための方向性も明確です。
- SNSでのストーリー発信(バイヤー・生産者・調理法)
- 美味しいけど販路がない生産者募集のネット発信
- 地元生産者や料理人とのコラボ商品
- ファンコミュニティや限定試食会
- オリジナル弁当・飲食店の展開
- 高齢者向けや健康志向向け商品の開発
- おいしさのエビデンス化(糖度・鮮度・栄養価など)
特に「おいしいのに販路がない生産者」に向けて自社の存在を発信することで、さらに強い仕入れネットワークを構築できると感じました。
まとめ:理念を“本気で”貫いた企業は強い
まるおかは、「安さ」ではなく「おいしさ」という価値を徹底的に突き詰めた結果、他のスーパーには真似できないポジションを確立しました。
この事例が教えてくれたのは、
「理念は飾りではなく、覚悟を持って実行したときに『武器』になる」ということです。
中小企業こそ、自社の“本当に大切な価値”を明確にし、それを愚直に伝え続けることが、長く愛されるブランドづくりにつながるのだと感じます。


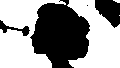
コメント